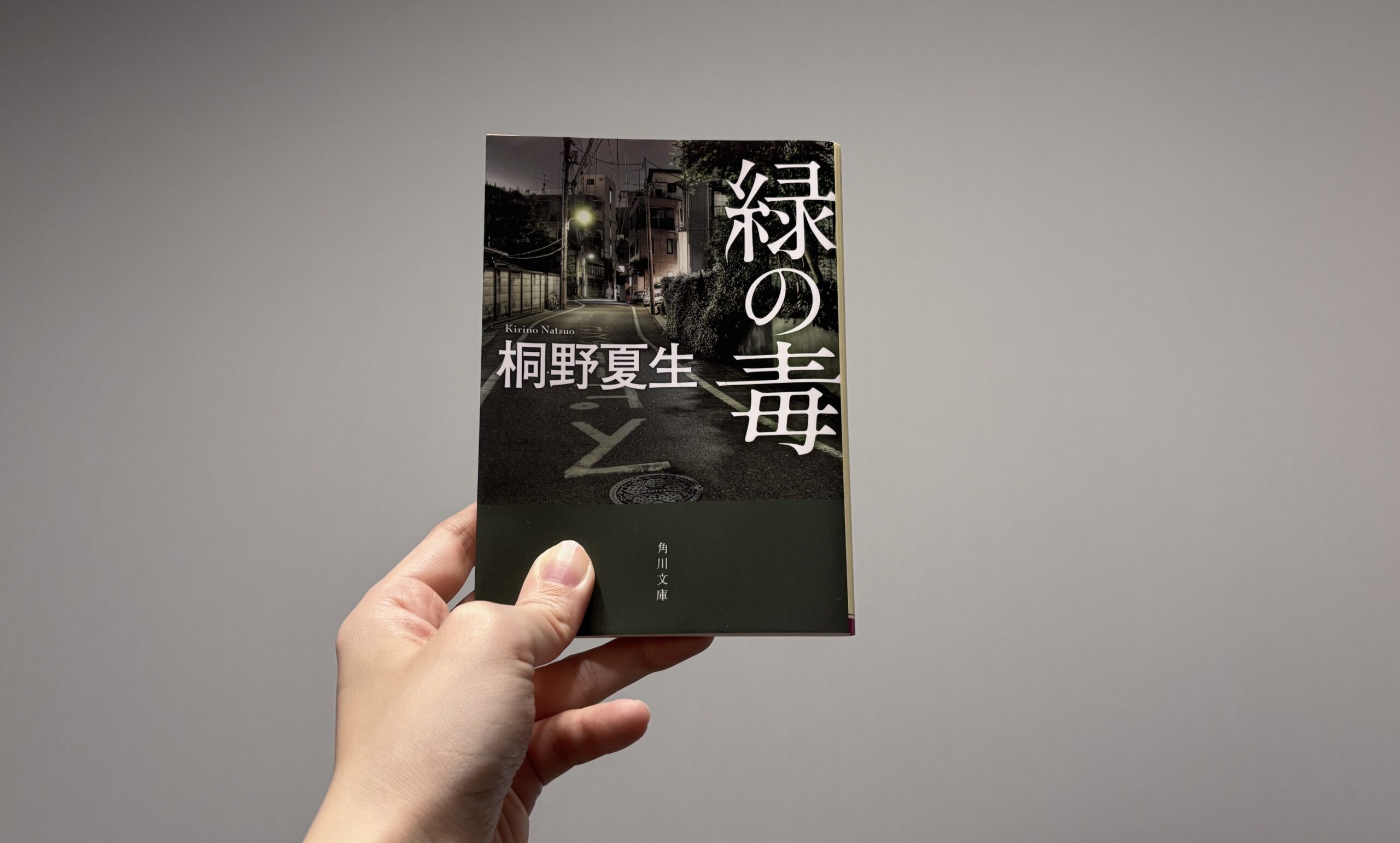本の持ち方が気持ち悪いことには触れないでほしい。
少し前に、桐野夏生の別作品『インドラネット』を読んだ。こちらを読んだ時にも主人公の男性に対して「おいおいTwitterにいる男のようだな」と感じたけれど、『緑の毒』の主人公である川辺もTwitterにいる男性のようだった。
Twitterにおすすめ機能(フォローしていないのに勝手にツイートをおすすめしてくる)がついてから、男女が主語になった争いが頻繁に目につくようになった。様々な嫌な言動を目にして、「こんな言動や行動をとる男女が身近にいなくてよかった」(いるかもしれないけれど表面上はそうは見えない)と感じている。
『緑の毒』の主人公の川辺は、リアルでは絶対に関わりを持ちたくないような「Twitterで争いを繰り返し女叩きモンスターと化した男性の成れの果て」のような自己認識と行動力を持った男だ。
その川辺と戦うために立ち上がる女たち。まるでTwitterの争いがそのまま物語になったかのようで、途中まで「本当にありそうだな」、「こんな事件が起きてもおかしくないな」と思い、ノンフィクション作品を読んでいるような気持ちになる。Twitterから飛び出してきたような男性を書くのが上手すぎる。
『緑の毒』の初版は2011年。2011年に出たとは思えないほど、現代すぎる内容だった。私と同じようにTwitterに住んでいる人であれば2025年発売でないことに驚くだろう。「Twitterの成れの果て」だと表現したことにも納得してもらえるはず。
Twitterに長く住んでいて、頻繁に見かける男女が主語になった争いに辟易としている人にこそぜひ読んでもらいたい。ただし、いわゆるレイプが主題になっているため(具体的な犯行の内容は描かれていないが)そこだけ自衛のほど。
川辺の行動や心理について、一貫はしているし、理由もすべて描かれているもののどうしても理解できなかった。「なぜそこまで?」という疑問が付いて回った。読了後に「緑の毒の意味」を調べ、タイトルの意味がわかって、ようやく「それならそうなるか」と納得ができた。
桐野夏生、Twitter男性に親でも殺されたんかと思ってWikipediaを開いたが、そのような事件は載っていなかった。ただ、親でも殺されていなけれ、身近にいなければ書けないような男性を描くのが本当に上手すぎる。思春期に読んでいたら男嫌いが加速していたかもしれない。